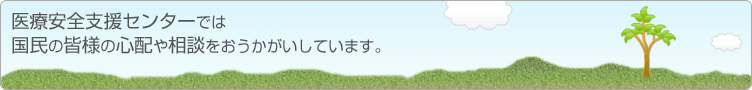
医療安全支援センターでは、さまざまな医療に関する相談について、解決の糸口を探すお手伝いをしています。
- 多くの検査を受けたが、検査の必要性が理解しづらい
- 主治医以外の先生の話も聞きたいのだが、主治医にどう切り出してよいかわからない。
- 手術後の経過が思わしくないのでカルテの開示を求めたいが、お願いできるのか。
- 院内処方と院外処方とは何か違いがあるのか。
- 現在使用している薬の服用について詳しく知りたい など
- 患者・住民と医療提供施設との信頼関係の構築を支援するよう努めること。
- 患者・住民と医療提供施設との間にあって、中立的な立場から相談等に対応し、患者・住民と医療提供施設の双方から信頼されるよう努めること。
- 患者・住民が相談しやすい環境整備に努めること。
- 相談者のプライバシーを保護し、相談により相談者が不利益を被ることがないように配慮する等、安心して相談できる環境整備に努めること。
- 地域の医療提供施設や医療関係団体の相談窓口や関係する機関・団体等と連携、協力して運営する体制を構築するよう努めること。
- ・都道府県、保健所を設置する市及び特別区
※「全国の医療安全支援センター」参照
- 患者・住民からの苦情や相談への対応(相談窓口の設置)
- 地域の実情に応じた医療安全推進協議会の開催
- 患者さん・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関、団体等との連絡調整
- 医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供
- 研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上
- 医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提供
- 医療安全施策の普及・啓発
など
医療法
- 第六条の十三
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
- 一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
- 2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
- 3 都道府県等は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
- 4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一八法八四・追加)。
- 第六条の十四
- 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
(平一八法八四・追加)

